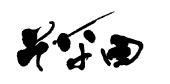翌日の出来事。②
その頃の僕といったら、まるで貧血を起こした大きな馬みたいに
体から毎日、どんどん自信が流れ出ていくような思いでした。
この情緒のかたまりのような一軒家といっしょに
毎日なにをしていいのかわからなかった。
初心者に高級車を与えたようなものでうまく操縦ができないのです。
今までこの道で食べてきたというのに
街はずれの古民家で店を開いた途端、自分が雰囲気にのみこまれ
来る方々への自分の接し方に大きな迷いが生まれていました。
どんな話をしてよいのかわからない、
どういった料理やお酒を出してよいのかわからない。
どう過ごしてもらいたいのかきっかけのひとつも見つからない。
完全に自分や店のあり方を見失っていき、いつしか
「素敵な空間ですね」という言葉に嫉妬心すら芽生えていました。
恥ずかしながら、初めて自分をみじめだと思いました。
そんな自分だけに向けたあわれみから離れたい夜には、あの店に行きました。
カウンターの端にはいつもちがった女性がひとりで主の方に話しかけています。
僕はふだんあまり飲まないウイスキーを舐めながら
知ったような顔で葉巻を吸っていると会話のかけらがなんとなく耳に入ってきます。
「だからマスター、あたし言ってやったのよ」
「先日はどうもありがとうございました」
「うん、じゃあ最後に一杯だけ」
「今日は来られないって。さっき連絡が来た」
主の方は、いつもひとりひとりの女性のお客さんと清潔に親密そうでしたが
点々と男性のおひとりも多かったように記憶しています。
その夜はカウンターの奥に見知った男性を見つけすこし驚きました。
彼がそな田を設計してくれた建築家だったからです。
――つづく。