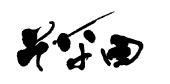「ドイツ製のジンを飲む」
陽射しに角度がついて、静かに夏のはじまりを告げる夕方でした。
気に入っているTシャツが通す風に、すこし機嫌がおさまり、いつも混んでいる馴染みのバーに連絡もせずに寄ってみるとすんなり通され、そういえば日中の赤信号にもあまり捕まらないでいたことを思い出す。
席についてジンを頼むと小さく品の良いグラスに注がれる。
おやすみですか。
とマスターより尋ねられるのを、そうですね。
とこたえたものの、この2年ですっかり遠慮と慎重が板についてしまった世相のことや、今日は、感染による大口予約のキャンセルに心が折れ、臨時休にした事情は話さずにいた。今、この店にですら他に客がいないことを見れば、あるじは僕より年下なのにはるかに上等な忍耐力があると思われたが、せっかく休みにした宵に余計なことを考えるのはやめてちびりとやった。
この、ドイツ製のジンは冷たくも熱くも感じられ、風味がうつくしいと思って飲んでいる。食道から胃まで一本に流れていくと気持ちがおちついた。こんなに素晴らしい雰囲気を、来号あたりのこの連載にでも、と思って勝手に文にして読み返すとどうも心もとない。おさまりのわるい流れと貧相な表現が目につき鼻につく。
きっと素人手腕の問題だけではないだろうと思っていたら、手厳しいと評判の、編集の仕事をこなす友人が指摘をしてくれた。
きみの文章には人に寄りそう感じがないからな。
言っちゃあ悪いけれど、人間の弱いところをみつめて許す幅を持っていない人柄が露呈しているもんなあ。ハハハ。
なるほど。と、平静のふりをしつつ合点がいく。と言うよりも本当は返す言葉が浮かばない。確かにそうなのだった。私は私のことをすっかり棚に上げきって、しかもそこから人様に指を差しながら正しいことばかりを話している。嫌な気持ちになると、自分のせいにするのは申し訳ていど、あとは誰かのせいにする癖が治らない。酒に飲まれる人間はきらいなくせに、自身には思い出さないよう、塞いだ夜が何遍もある。
若い頃、東京に暮らしていたことがある。あの街で人生初の賞与をもらった勢いで当時気に入っていた女性と青山のバーに行った。
泡だ白だの赤だのなんだと、ワインを痛飲してしこたま酔った勢いで、同じ並びのカウンターで、5席も離れた常連と思しき紳士に赤ワインを引っかけてしまった。正確には、彼によく似合う(だろうはずの)椅子にかけていた白い麻のジャケットに、だった。本来なら届くはずの距離ではない。
私は、置こうとしたグラスを誤って倒す刹那、勢いよく手を伸ばして転倒を防ごうとした。それがすべて良くなかった。私の指は(それは見事に)グラスの脚を払う所作となり、大ぶりのリーデルグラスは弧を描き、真紅の液体を虚空に吐き出しながらジャケットに接地し、堕ち、粉々に砕けた。
その音が合図のように、これほど人が居たのかと思うほど、火事場を納めるスタッフが店の奥から出てきてジャケットに駆け寄ったものの、誰の目に見ても紳士の真夏の一張羅は、血塗れの即死であった。謝るマスターに紳士は、いいからいいから。と言って微笑んでいた。
呆然とその場に凍りつきながら私はいまだなんらかの体裁を保とうしていた。つまり、それはどうにかして時を戻そうと言う相談に等しかった。私は当時からその程度の男なのである。ようやく、いちばんのそれは、謝罪であることに気づき被害者へ近寄り、こう言った。
もうするわけあるません。
発した言葉の不出来に、店内に空っ風が吹いた。それから紳士の品格ある口髭が小さく動いた。「次にやったら怒りますよ」あのとき誘った女性のことを、私は恥と未練と共に覚えているが、彼女は私の名前すら覚えていないだろう。
その真夏から25年ほど過ぎて、今、自分の人間の幅はいかばかりかと思う。いっそのこと、このお気に入りのTシャツを誰か汚してはくれまいか。そのとき私は何と言うのか。
この店は、その答えをさぐる時間をくれるバーである。と書けば格好はいいが、これは正確ではない。何ぴとにも寄り添ってくれるバーなのである。
今回の不親切案内
バーR
すすきの交差点から北西に徒歩3分、タマゴのオブジェがあるビル10階
日曜休