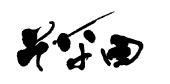とんかつを食べる。【R18指定】
「とんかつはちょっとしたごちそうだと思うんです」
そう話したのはとんかつに詳しい常連さんで。彼のとんかつ愛は趣味から始まり、ここ数年でとんかつ屋のプロデュースに及んだかと思えば
今ではテレビのとんかつ特集でコメンテーターまで務められるのですから、彼の目利きと世の中のとんかつ愛は人知れず奥が深い。
彼曰く、肉汁をとじこめた美味しいとんかつに感動した際にその「ちょっとしたごちそう感」を抱いたそうで。気軽だけどごちそうされたら嬉しい、そしていいことがあった時にひとり食べても楽しい
――ちょっとしたごちそう、とんかつ。
確かに。
くらべてみれば、天丼やうな重は完全な「ごちそう」ですし、フレンチのフルコースやおまかせのお寿司はもう一段上の「ぜいたく」という気もします。一方でとんかつはその実ちょっとした定食のような見た目でも、――無口なまでにその主張をひそめた――かじりつくとあふれ出る肉汁の旨味は一瞬で食べるものを虜にする。この裏腹なギャップこそが「ちょっとしたごちそう感」なのかもしれないな、と思うんですね。
僕も、その彼のとんかつ愛にふれてから時折ひとり、とんかつ屋さんに通うようになりました。伺いはじめのときは運ばれてくるまでの時間に手持ち無沙汰感もあったのですが、慣れてくると読みかけの本を持って伺うように。待ち時間というのは、極端に短いと不審さが漂って「ちょっとしたごちそう感」がわきづらい。言わばこの待つ、という行為はゆとりがないときにはまごついてみえる、美しくも鈍重な海亀みたいなものなのかもしれないですね。
さて、僕にとって数度目かのとんかつ屋巡りは予定にはなかった秋の長雨が降る休日で。
朝からひとり、映画を観たあとの灰色の街並みの昼下がり、これからどこへ行こうかとあぐねていると通りの向こう、傘もささずに腕を組んだ若いカップルが大手のとんかつ屋の軒先にあるサンプルメニューを楽しそうにのぞいているのが見えたんです。すると不意に思い出したんですね、それはすっかり忘れていたずいぶん情け無い色恋の顛末。
事実は、かっこよくならない程度、そして噓つきにならない程度に微調整を加えて以下――。
――今から20年ほど前、東京に暮らしていた僕の20代のはじまりはほかの同世代と同じく、刹那的な暮らしにいつもお金などなく、仮にもちあわせていようが遊びに使いきるぶざま。
そういう頃に、よく二人で会っていたすこし歳上の女性がいました。彼女は、名前の中に色の名が一文字入った、瞳と肌の色が淡い女性でした。ある熱帯夜、意味も理由もさほどないまま、僕と彼女はしこたま酒に酔ってーーおそらく東京では毎夜、または何百万組の男女に繰り返されてきたエピソードをなぞるような交際が始まりました。
僕は彼女を呼び捨てにはしませんでした。できなかったという方が正しい。それは年の差ではなく、彼女が大人びていたことでもなく。いつでも、酒の酔いから醒めてしまえば、どうしてこんなに美しいひとが僕の恋人なんだろうという疑問が、彼女にフラれるその日まで解けなかった、ということが大きかったように思います。
彼女は待ち合わせ場所で会うとかならず小さく微笑み、僕の左側を歩き、僕が左脇につくる小さな輪に自分の右手を休ませるみたいにあずけてきました。まるで「頼りにしてますよ」と言わんばかりに。
そして彼女は彼女の気持ちをあらわすとき、
それはたいてい言葉に頼るものではありませんでした。日ごろより無口な彼女は、微笑むかうつむくか。そういう二進法だけで感情を出すことが多かった。そしてその頃の僕はそういうひとを格好いいと思う時代の全盛でした。
だって僕は全力でコミュニケーションをとっているというのに、彼女ときたら最大限の感情を最小の身ぶりだけで伝える、それだけで僕のような、まるでファンのような恋人ができるなんて。そう書けば大げさですか。それでもこの恋に、青年の口角は上がり、日々の心はじゅうぶん浮つきました。
こうして20代の僕が出会った大人の女性とのつきあいは、
僕と、僕の生活を大きく変えようとしました。
部屋をまいにち綺麗に保とうとしたり、見かけた生活品をふたりぶん買いそろえてにやけてみたり、美味しいと評判のお店を調べて覚えてみたり、毎朝かがみを見て寝癖を直す習慣が身についたり。
彼女はそのたびに、微風がレースを揺らす程度の笑みでこたえてくれる。それがなにより嬉しいのですから、恋愛というものはとても安上がりな反面、その意気込みと手間だけは、営々黙々と竹ひごを編み続ける職人のような実直さをまとっていたりするわけです。
余談ですが、英語にある、クレイジーフォーユー(Crazy for you )という言いまわしは、よく「あなたに夢中」と言ったりしますが、それではずいぶん生やさしい訳ではありませんか。ひとの本当は、ほんとうに自分以外のだれかに狂ってしまう時があると思うんですよ。
さて。
神奈川に住む彼女と、当時を高円寺に暮らした僕たちのデートはいつも交通の便がいい新宿でした。駅の南口で待ち合わせて軽くお酒を飲んでは、将来の夢(!)について青年が語ったりするような稚拙なものでしたが、ある日、青年のわがままな愛情は思いつきの提案をします。
それは彼女の好きな美味しいお肉を食べるということ。
しかし唐突である分、焼肉や鉄板焼きとは懐事情と合うはずもなく、ぱっと閃いたのはくだんの
――ちょっとしたごちそう、とんかつ。
しかしながら、今ほど調べ方がなかった当時には急な対応力もありません。季節は東京の長い夏がようやく終わりかける、少し寒さを覚える秋の夕方、街を進む若いカップルの針路は頼りない青年によって難航していました。
微笑みながら「どこでもいいのに」と僕を見上げる彼女の優しい言葉がかえって自分のふがいなさを慰められたと、見栄を奮い立たせるのは幼い男の性。どうしようもない、塗る薬も飲む薬もないばか。
むやみに進む僕の左で彼女がめずらしく言葉をつづけました。そしてそれはおそらく僕たちが付き合いだした数ヶ月の中で彼女がいちばん多く発した言葉であり、そしておそらく当時の僕にとっていちばん幸せな会話。
「どこでもいいと言ったのは」と言って彼女はすこしだけ微笑みました、
鮮やかに思い出します。「普段のわたしはあまり食べないでしょう?」頷く僕に続けます。「あまりお腹が空かないのね、もちろん体型を気にしていないといえば嘘になるけれど。それでもおなかはあまり空かないの。最近読んだ本に書いてあったんだけど、男女が食事をするのはあたりまえだけどエネルギーをとるだけじゃなく、もうちょっと深い意味があるんだって」
そう彼女が話したときに大手のチェーン店のとんかつ屋が目に入り彼女が「ここがいい」と言いました。
席に通され、丁寧なお辞儀を教育された若い僕らくらいのスタッフが出してくれたお茶を受け取りながら彼女は続けます。
「もちろん生きるために食べるという以外に、コミュニケーションを深めるみたいなことはあなたも知ってると思うけど」
そうだ、彼女は僕のことをあなたと呼んでいたんだった。
「でも本当は“そういう”欲を掻き立てられない男と、女は食事をしたがらないものだって、その本には書いてあって、わたしはとても納得したの」
“そういう”欲――。
少年とさほど変わらない青年は「“そういう”欲って?」と底抜けに間の抜けた声で聞き返す。しかし彼女は、またいつもの彼女に戻って微笑むだけ。いま思えばかすかに彼女の顔を紅潮させていたのは待つ間に飲んだビールのせいだけではなかった、と大人になった今ならわかる、か。
はこばれてきたとんかつ御前は彼女がヒレで僕がロース。彼女は僕にまずふた切れか三切れくらいくれた気がするけれど、僕のとんかつをあげようとしても微笑むだけの姿がずいぶんやさしかった、それが記憶通りだとするなら嬉しい。そして、適当に思いつくままはしゃいだ時間を終わらせたくなくて
二軒目の店をあてもなくどこにしようかと新宿の街をだらだらと歩く。
しかし、その日が僕らのピークだったように思います。
たしかその日からわずかひとつきほどで、蜜月だと思っていたのは僕だけだと、唐突に思わされたとある雨の週末の待ち合わせ。
遠くからでも見つけられる彼女がうつむきながら歩いてくるのがすこしだけ引っかかっていました。彼女は付き合ってから初めて、その右手をあずけてはきませんでした。
気象図が読めなくても、かすかな匂いで雨降りを確信するように、
どこか不安を感じた僕は筋ちがいな憤りと、かすかな勇気を持ち合わせて彼女に理由を尋ねると沈黙――。
変な勇気なんて出さなきゃ良かった、と当時は思って聞き出した言葉は、今では至言のひとこと。
「あなたは自分が語る夢に対して日々の努力が追いついていない」
頼りなかったんですね、ものすごく。
そしてやはり、やっぱりだらしがなかった。
それでも、切なさや悲しさみたいな感情は、負債と資産のような対等なバランスで、幸せだったもう一つの記憶もしっかりと呼び起こしてくれるもので。僕たちの関係がピークだったあの日、東京には空がない、かつてそう言うひとも居ましたが、実はその広がりをどこまでもみせた新宿の秋の夜空を見上げながら腕を組んで歩く僕たちはとんかつを食べてお腹いっぱい。
ふと僕が、ほどけた靴ひもを結び直すのに屈んだとき。
彼女が僕の左耳に近づいて囁いたひとこと。
それは無口な彼女がひそかにとじこめていた、
熱意によく似たちがうもの――。
「あなたといるとお腹が空くわ」