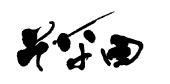瓶ビールを飲む。
夏のはじまりに飲むビールは小瓶にかぎります。
近所の、お住まいと一緒になっているはずのスナックのあけっぱなしの入り口、その薄のれんが宵の風で呼吸するようになる頃、ひとりでうかがう小瓶がおいてあるカウンターくらいの小料理屋さんが恋しくなるんですね。これはもう連想のクセみたいなところで、夏に花火、または、雨の染みをつくるアスファルト、いわし、カブトムシ、鰻、水まんじゅう、繁る森、ホースからあふれる蛇口の水で冷やされる夏野菜、それぞれに思われる風物詩があるように、夏のはじまりは小瓶で飲むビールがよろしいように思います。
ただこういうお店が札幌ではなかなか見つからないんですね。さがしてもさがしても見つけられないうち、どなたかにお誘いいただいたお店にお供したタイミングでいつの間にか忘れてしまう。
そうしてまたつぎの週末が近づいてくると、小瓶をかたむけのんびりカウンターにいる居心地を想像して、またふらふら探しはじめる。かりに見つけてもこの人間はかなり好みのゆがんで狭いところがありましてその瓶ビールにも、これ、という好みのグラスがあります。実際に本当にそう思い込んでいるものですから、この男はそのグラスでなければすこし残念がるんですね、大したことではないくせに。
ただ特別なぜいたくは言っているとも思いません。好みのグラスはただひとつ、おじさんたちが「いやいやどうも」なんて言い合って注ぎあうときに添え手で持つビール会社のロゴがうすくなった小さなコップ、あれです。
そう書いてみると日本のビールはサラリーマンの歴史と言っても過言ではないと思うんですね。
サラリーマンの方々が仕事の終わりにひとり、あるいは複数で飲むビールを、みなさん生活の句点や読点のようにしながらリズムをととのえ明日にそなえる、その積み重ねであったように思い至るからでしょうか。僕が小瓶のビールを好むのもそういった遺伝のようなものがあるかもしれません、ステレオタイプのようでもあるけれど。
ざっくりまとめますと、休日の僕のささいな希望のほとんどは小料理屋のカウンターで小瓶のビールをいただくことで占めています。ですから肴はなにがいいかと言えばあまり「いいもの」じゃなくていいんですね。かといって、「枝豆」だけではすこしさびしいもんです。あってじゅうぶんありがたいですけど、でも「とれたてのだだちゃ豆」だとすれば少しばかり気障ですか。ふわりと湯気立つさやに塩がぱらりと浮いてるのを見つけたら少し緊張して、ほかにも「なにか今日のおすすめを尋ねながら頼まないと悪いかな」、そんな(お店の方に)よけいな気をまわしかねない。なんとか産の〇〇を△△して…とつづくような当店の料理では瓶ビールがぬるくなってしまう。ですからこんな面倒な客には葱となにかの貝のぬた、こっていても精々ブロッコリーと〇〇の塩炒め、そういう肩の力の抜けた目の前のおばんざいをそのままいくつか小皿に入れてもらうくらいがちょうどいいわけです。
ちょうどいい、という感覚は一番のごちそうなわけで、名店にはそういうものが多いですね。東京にいたころ、ひょんなことから知りあって十数年のおつきあいになる古い小料理屋さんがあるのですが、そちらはまさにちょうどいいわけです。ご夫婦は人懐っこい(失礼!)ところがあるのにかかわらず、僕が一人でカウンターに腰かけ、飲みはじめると二言三言声をかけてくれてあとはおしまい。
「おう、おのでらくん元気だったか」とご主人、
「あらすこしやせたんじゃない」と奥さん。
何回行ってもかわらず出てくる、だだちゃ豆ほど高級ではないけれど、慣れた手つきでゆでられた枝豆のようなごあいさつ。
時おり聞こえるご主人からの「早く持っていけ」「持っていくわよ」という奥さんの売り買いのことば遣いが聞こえるけれど、まだ空気があたたまっていない寄席の落語のようでどの客もほとんど聞いていない。
おふたりのお店はわけあって場所などを正しく書くことはできないけれど、僕も生まれるはるか前、ご主人は事情のあった奥さまをまるごと受け入れて一緒になられた。愛して受け入れてまわりの関係するすべてのつながりを笑ったり怒ったりすねたり、そうして生まれたつぎの命を喜んだ。今でもご主人はその仕事同様手抜きすることなくご家族と暮らされているわけですが、一度、ご夫婦に近しい方からもれ伝わった事情が僕の耳に入ることがありました。
きっと葛藤もあったに違いない(事情だ)とも思えたのですが、みじんも態度に見せないどころか“傷”の影すら感じさせない。だからだれも気づかないし、気づいたってだれも何も訊かない。その店に通ううち、ご主人は迷いなんて浮かばなかったのかもしれないし、ましてや傷なんてまるでつかなかったのかもしれないと考えるようになっていつのまにか忘れた。
時おりカウンターで小瓶のビールにありつくことができると、少しだけ自分の過去と今と先について考えてみることもあるわけです。そういうひととき、あのご夫婦、とくにご主人のことを思い出してみます。自分は彼の選択ができるだろうか。人を受け止められる自分ではとうていないけれど、この先はどうだろうか。まわりの人を肯定しながら仕事をしているだろうか、少しはそうしていけるだろうか。人のために働いて、夜半の晩酌で互いに労をねぎらうおふたりを、いい年をした自分が美化しすぎるつもりはないけれど。――そう思うとまた空になった古びた小さなコップに瓶をかたむけ、あてのない思考レースをビールとすこしの疲れで鈍くなるまでむさぼるわけです。
そういった、さほどの価値もないひとりの休息を楽しむには、小瓶くらいの量がちょうどいい、という気がするのです。
店主 小野寺弘祐拝