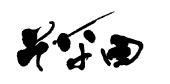ロングモーンを飲みながら
「親父は、おれが生まれるまで働いたことがなかったんですよ」
そう話してくれたのはこのバーで何度かお見受けした同じ年くらいの男性はいつも1人。夜更け。
ぼくは数人でお邪魔することが多いのですが珍しくこの夜はこちらもひとり。
壁に、まるで綺麗な歯並びのように揃えられたウイスキーをそろえる女性店主が選ぶ品は二つ。ひとつは古き良き歌謡曲を交えた音。そして、ウイスキー。その中から、彼と僕がお互いに「ロングモーン」というシングルモルト好きということで意気投合。
彼は「この蒸溜所は1890年代の創業からどんな不況にも一切休業することなくウイスキーを作り続けてるところがすごいと思うんです――それに比べてうちの親父ときたら」そう話して、冒頭の言葉に戻るわけです。
ただ――、そう話して彼はトワイスアップでひと口舐めてつづけます。
「おれが小学校5年生の時、家族の夕飯を作っていた母が肩の痛みを訴えたんです。ひどく痛がったんですね。でも田舎でしたから冴えない診療所に行って、夜中には亡くなったんです」
視線を彼にやりそうになり、あわてて止める。平静を装う。
「心臓の病が時々関連痛としてそういう肩の痛みとして出る場合があるそうです。あっという間のことでした」
女性店主は離れたところでボトルを眺め、流れてきたのはいっそセレナーデ。
「悲しい気持ちなんてよくわからないんですよ、子供でしたし、突然でしたし。葬式が終わって初七日が過ぎたあたりで父親とふたりでなんか腹が減ったな、という話になって」
窓の外の人並みは依然なく、客足は近いか遠いか迷いのさなか。
オレンジ色の街頭が店内のステンドグラスに差し込み店内に光をあてる。
「すいません、自分だけ話してしまって」
ロングモーンのほのかな甘みが風を呼んだと思ったのは店主がつけた送風でした。
「父はスーパーで働いていました。おれは父と手を繋いでお惣菜を買いに行ったんです、とてもたくさんの。少し前まで働いたことのないボンボンだった父親ですから買う量も目見当なわけで、両手に食い込むほどの量の重さで痛いほどでした。それをぎっしりと冷蔵庫に詰めたんです。初日も二日目も男ふたりで食べ続けるわけです」
次にかかり出したKenny Gのサックスがこの場に浮かんだなにかを慰める。
「また朝が来て冷蔵庫を開けると、もう腐ってるんですね、惣菜が。あわてて父を――親父を呼びました。ご飯がないって。食べるものがないって。その時、ふたりで冷蔵庫にびっしり詰まった傷んだお惣菜を見ながら僕たちは泣いたんです、どうしようお母さんが死んじゃったって」
そう言って彼は少しだけ微笑います。
「後にも先にも父が泣くのも、ましてやふたりで泣いたこともありません」
接客業の経験からこういう時は「そうですか」という返答以上のものをないことを僕は知っています。
「その親父――まあもういいか――父も今日で初七日を迎えまして」
もしや、と思いグラスを持ち上げてみると彼が笑う。
「そうです――父さんの好きな酒だったんです」
――やがて、すべてのひとがいなくなる。
でも遺されたものがウイスキーのように瓶の中で人知れず色味を増していく。時代を紡ぐ。そう語るには綺麗すぎる、雑すぎる。
失敗も多い。失敗の方が多い。
しかし。生きたいと願う者の魅力は――。
Bar 「T」タマゴのビルの西隣の赤茶けたビル3階 日曜休。