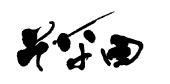稚鮎を食べる。
こうしてもう、かれこれ8年以上毎日食べ物屋をやっていると食べ物に困る、
ということは決してないのですがせっかくの休みに何を食べるか、ということにあぐねることは多々あるわけです。
ここ最近なら――とくに陽の長くなりはじめた5月の日曜の昼下がり、
自宅のベランダに出て和紙のように乾ききった洗濯物をとりこみながら、
数時間後の日暮れ頃、じぶんの気分にあいそうな食事場面をいくつか想像してしっくりくるところを探す。
ひとつ目はお店の方に見つくろってもらった数品の、こじんまりとしたおばんざいを宝もののようにならべながら、瓶ビールを手酌でグラスにかたむけているところ、
または潔癖そうな白木の鮨屋のさらしで刺身を待つ間に燗酒をちびりとなめるところ、
最後にラギオールのナイフとフォークにはさまれた小空間で、大ぶりなワイングラスをするするとすべらせながら「◯◯のテリーヌ」という感じの、小洒落て気の利いたひと品の前で、という場面。
しかしながらそれぞれの自分を思い浮かべながら、ひとりごちてみたりしてもいかんせんどれもしっくりこない。
そう感じるのは当然お店のせいであるはずはなく、「自分自身とお店との距離感が大切なんです」と教えてくれたのは着付けから手紙の文面、果ては旅のたしなみにいたるまで造詣深く、そして優しく美しい知人の女性でした。
その方とは過去幾度となく共通の知人たちとで食卓を囲む場に僕もお邪魔するのですが彼女はとかくスムースで、むしろ、おみそれするのを通り越して
「ひょっとしたらただの紛れ当たりではないかしら」と思うほど、羽根のようにさりげない気づかいをうけていたことを後から思い出すこともしばしば。
いつも、彼女が外食先で箸おきを使うその作法は、それが用意されていなければ、そばにある小さな盃や豆皿を代用し、それらでは角度がつきすぎ、滑るとなればいつの間にやら彼女が小さくたたんだ箸ぶくろが、箸おきに姿を変えているのでした。
同じようにされる方も多いかと思いますが彼女の場合、同席している我々の知らぬ間にひょいと元箸ぶくろが箸先をもたげる役を買って出ているのです。
それはいつかの春の初めころでしたか、地下にあるワインバーで酔いにまかせて小さく考察してみたときに気づいたことですが
彼女はその時々の話し手のエピソードをただ傾聴するだけでなく、いつの間にか相手を自然に、しかも数度にわたって気づいた部分を率直にほめたたえているのです。
そうされた側はいつの間にか彼女や僕たちにいろいろな楽しい話を聞かせてくれるようになりますので、
全員の目線はその時の話し手に集中していることになります。
そういったタイミングで彼女は靴紐でも結ぶみたいに箸ぶくろをくだんの休み座にしている、とようやくこちらが気づくわけです。
よくある会話の中で、異性の魅力を語るときのひとつに 色気の有無が話題に出ることがありますが、
彼女のそばで過ごすことが増えるたびに、実は色気という感情の喚起というものは、決して人口甘味料のようなべったりとした口紅とか、ましてや一部の男性が勘違いして時折しでかす、あの、あえて冷たい態度をとるような狙った印象操作ではなく、むしろ彼女のように、誰かと過ごすひとときを自然に楽しむ姿勢と、その影で誰に知られるわけでもなくひっそりと箸おきをつくる秘密の指さき――そんな静と動の小さな落差こそが色気の正体なのではないかとも思うわけです。
5月の半ばでしたか、料理長が「稚鮎を仕入れてもいいか」と訊きます。
それをぜひ、と僕が応えた数日後の夕方、そな田の二階(当店は一軒家ですから)の小部屋でためてしまった机仕事をいそいそこなしはじめていると料理長の手元のベルが短く僕を呼びます。
降りて見やると料理長は発泡スチロールの箱内に用意された簡易的な水槽にゆらゆらと行き場なく泳ぐ十数匹の稚鮎を見せたかと思うと、その大きな右の手で一匹をそっとすくい上げつつ左手に用意した串をパクリと空いた口から尾びれにかけて体内へと一息にすべりこませます。すると、内臓に穴があいて空気の入り込んだからでしょうか。ちう、というかすかに鳴き声のような音がしますと稚鮎はエラのすきまから鮮血を流し束の間、かすかに暴れます。
つぎつぎと手際よくすくい上げられた小ぶりな川魚はその、ちう、という音をたてては用意された火まわりに並べられていき一様にかすかに暴れるのです。一体どうしてなのか、僕はなぜだか良いものを見たような気持ちになってしまい、たまっていた机仕事が急にはかどるようになります。
そして数十分。
再び短く店主を呼ぶ料理長の短いベルの音は稚鮎の焼き上がりを示すものでした。
作業中の他のスタッフの手を思わず止めさせ振り向かせたのは「おいしいい」そう感嘆した僕の声があまりに大きかったからでしょう。
その身の薫りに、甘味、そして内臓のほろ苦さが一体となった稚鮎はすでにそれだけで一皿。
何か足すのはひどく野暮と感じるのは決して過言ではなく。
鮮烈だとか芳醇だとか、そういう誰かが選びそうな形容句も、「稚鮎独特のほろ苦さこそ食べる者へのかすかな抵抗である」という易いたとえも、生命をいただいているという建前同然のそれも、思わずおお声で口をつくうまい、の言葉の眼前には無力だと食べ物の扱いをなりわいとする本人が気づく。まさに今始まろうとする初夏の宵。
ちう、と小さく鳴き、束の間、すこしだけ暴れていた稚鮎を食べるということは、見える色気にすこしだけふれるということ。
店主 小野寺弘祐拝