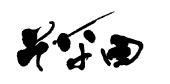翌日の出来事。①
2010年の10月に開店したそのころ、
よくお邪魔していた照明の暗いお店がありました。
本当はもっと前に何度かうかがっていたのですが
その、年上の人びとが通うような店のハードルの高さに足が遠のいていました。
それがどうしてもう一度通うことになったのか、
僕はそのきっかけをはっきりと覚えています。
諸先輩の言いつけを守って
「開店当初の2ヶ月は休みなく営業しながら」店を閉じた帰り道、
家と店の往復が続いていた毎日と、
定期的にやってくる空腹に耐えかねて街なかに出ようとしたのですが
疲れのせいか入りたいお店への鼻が利かない。
だらだら歩いているうちに空腹を通りこしてお酒が飲みたくなり、
そんなときに――ごくごく勝手に――足の遠のいていた、
くだんのお店が入る茶色のビル前に立っていました。
ひょっとすると開店したばかりの気負いもあり
「今の俺はあの時の大人の雰囲気も知らない子供ではない」
そんな自負があったのかもしれません。
とびらを開けて慎重な声色で「こんばんは」と声をかけると
なめらかな、気取りのないトーンで「いらっしゃいませ」と出迎えられます。
案内されるがまま着席するとかっぷくのいい大きな棚が目の前に広がり、
種々様々なボトルがきれいな歯並びのように敷き詰められています。
そして、そのコレクションに等しいようなお酒からは
専門的な威圧感やその種の店独特の警戒心などはみじんもなく、
「お好きなものを」という声だけが聞こえてくるようです。
僕はそのお店に大きな勘違いをしていました。
いま思えば、やさしくておおらかな、
そのお店の主の心がそのままボトルたちに反映されていたのだと思います。
そこは、ただただ清涼で重厚でやさしい空気の流れる、
ひとりになりたい誰かのためにあるような店でした。
――つづく。