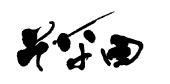そな田日記
【4/1「架空の名言、嘘の格言〜私はそんなこと言ってない」民明書房刊】
誰かが僕の映画のことを嫌いだとして、
好き勝手に悪く話せば話すほど
こんなに効果的で無料のCMはないよ。
———映画監督・デビッド・リンチ
秋にトナカイを食い溜めても冬には腹が減る。
———エスキモーの古い教え
いいか。結婚するということは
口座を3つにわけるということだ。
1つ目は妻の化粧品のため、
2つ目は子供の将来のため、
3つ目はそれに疲れた自分が逃げ出す時のためさ。
———ニコラス・ケイジ
人間が束縛を嫌がるなんて嘘です。
いつ、どこで、何をしているか。
誰に頼まれなくてもSNSに
絶え間なくアップロードし続けていることで
十分わかりませんか?
——— TikTok創業者・張一鳴
子供は水あそびの川を探し、
大人は水車作りの木を探し、
資本家はそういう村を探す。
———経済学者・ケインズ
変化がほしい。と話す人と
下手な釣り人は変わらない。
いつも同じ場所にいる。
———小説家・開高健
空からぶどうが落ちてきてからワインを作り始める?
自分で植えた方が早いし、なにより美味しい。
——— Opus one醸造家・ロバート・モンダヴィ
水に暮らす海老も、
自分を茹でる水は好まないものです。
———軍師・黒田官兵衛
人は器。その手入れにはやさしい言葉。
———モザンビークのことわざ
過去の写真が今のあなたを慰めても
未来のタッちゃんを励ますことはないの。
———朝倉南〜劇場版タッチより
エイプリルフールにもついてはいけない嘘がある。
“今度の政治家には期待できる”というものさ。
何故いけないかって?
この嘘に騙されるやつはいないからね。
———C.チャップリン
【シーシーウーとシャンパーニュ】
シーシーウーと呼ばれ活躍している音楽家の幼馴染がいます。
先日もあるツアーに帯同していて、
そな田は、偶然にもそのツアーのお食事を担当させていただく。
ステージ裏で、わざわざ演者ご本人より丁寧な挨拶をいただいたあと、シーシーウーから会場案内を受けていると、彼に気づいたファンの方からちょっとしたどよめきが起こる。愛想のいい幼馴染は笑顔で撮影に応じていて、僕はそこから離れて、すこし居住いを悪くしながら
この感じは、何かに似ているな。
そう思っていたら思い出した。そうか。素敵なお店で、シャンパーニュをいただいている時とおんなじなんだな、これ。うちの母は下戸で父はビールとウイスキー世代。和食もフレンチもお茶かいつも同じ酒の世話になるというこの田舎育ちの小せがれが、いつからかさらっとシャンパーニュを頼むようになった。
いつしか銘柄にも味にも詳しくなって、グラスの海底から湧く泡にそのときどきの思いをみるも、それがあたかも普段から。と言わんばかりに平常心を装って杯を重ねる。そうして酔っ払っては余計なことばかり話す。
この最後の部分だけが自分の根っこの姿。
——————————————————
シーシーウーとは、鹿討奏(ししうち かなで)。
音楽家で、この本名なのだから大したものだけど、僕らは彼を「かなで」と呼ぶ。だから彼がファンからシーシーウーという愛称で呼び止められて、撮影に応じたりしていると、どこか他人行儀にもなるわけです。
「僕は、彼のただの友達なんです」というのもちがうし
「ええと、関係者です」というのも当然ちがう。
つまり、誰にも聞かれてもいないことを先回りして説明しようとすること自体が滑稽で、かと言って気を抜いてこれ以上呆けた顔もしていられない。
そういう感じがとにかく居住まいが悪い。
シャンパーニュは酔って忘れてしまうけどこの幼馴染を取り巻く華やかな環境もさらっとシャンパーニュを楽しむ環境も、僕に用意された当たり前でふつうの環境ではない。
シャンパーニュや、かなでが素晴らしいのであって
それは僕のものではない。
———————————————————
じぶんの仕事が終わり、ステージを拝見した。
知らない曲までが、というよりファンに深く愛されている曲を中心に組まれた音の中で、この方々の、いまだ闘いをやめない姿勢に触れていると涙のように鳥肌がたってきた。その理由を考えていると、ステージから名前のつかない力を得たひとりひとりの観客の瞳が、暗転した会場のペンライトよりも輝いて海ホタルのような幻想的な世界が発生しているからなんだな、と気づく。
僕も、裏側のひとりとして(すべて知っているわけではないけど)開場までに走り回るスタッフの方々、響き続けるマイクテストの音、我々が運んだ食事を提供される方々の手際、公演成功への重圧を笑顔でかわす担当者。そして会場の熱。
すべてが「循環」している。
夏の空き地、青空が遠くにある中、かなでとふたり、お互いに好きな女子の話しや、おっぱいの話しかしていなかった僕らの時代はなにひとつ損なわれることがないまま、かなではトロンボーンを吹いて、あらゆる演者、そして観客の皆さんから愛されていて、良かった。
あの夜、その世界には悪口みたいな余念がひとつもありませんでした。
そうして、一日のすべてが終わって、かなでと2人、お疲れ様会をしていたら「寝てたべ」といわれて「寝るかよ」と言い返す。この音楽家は、音楽のこと以外、あまり人のことや世の中のことがわからないんだった。僕も、だいたい同じだからよくわかる。
この場を借りて、ご配慮いただきましたすべての方に心より感謝申し上げます。
【空飛ぶインチキ】
50歳という年齢がもう、郊外で見つけるコンビニくらい近くに迫ってくると、
世の中のインチキにそこそこ気づくことが増える。たとえば、人が好きなので接客業をしている。とか、子育てからは多くのことを学べる。とか。
いくら人が好きでも「お客さんから信頼をおかれるプロか?」は別案件。
(ごめんね)
先日も、子育ては学びが多くてとても素晴らしいのに、あなたはこどもを作らないの?と、子供が産めない知人にはっきり伝えている人を隣でみて、呆れも怒りも通り越して彼女と顔を合わせて「^_^」となった。
でも。
「愛してる者(物)から学ぶことが多い」って超ふつう!
(ごめんなさい)
そして。
みんなが苦手なものから学ぶもののほうが深みと強みが多くないですか?
税金の仕組みとか、フラダンスとか、英会話とか。
多様性を認めようぜ!と言い出したら世間がやたらぎくしゃくしてきた。
多様性にもインチキがいっぱい。
飛行機もおなじ。
機内で赤ちゃんが泣く。(彼らが僕を好きかは知りませんが僕は子供好き)その傍で明らかに疲労困憊の男性が寝られずに、でも、何か言おうものなら他の乗客からにらまれて空に放り投げられることを察して、
うーん、もぞもぞ、と少しでも寝ようとしている。
なんかもう、ふふっ。となる。ひどすぎて。空を飛べるほどの力を誇る会社が「赤ちゃんさんが泣くのは仕事ですから、みなさん協力して我慢しましょう」とモラルで縛るという力技。お母さんもCAさんもちゃんとわかってて、
《あ、この男性は疲れているんだろうな、ごめんなさい、我慢させてますよね。まずいな、お願い、もう泣き止んでー!》と焦ってる。
※モラルのない母親もいますけどそこまで広げる気は無いです。モラルの話ではないから。
問題は、空を飛べるほどの圧倒的な科学力を誇るのに、お客さん間のトラブルは「モラル」と「泣かせないコツ」くらいでしばるセコさよ。大切なのは吸音、防音対策かなと。
(赤さんが)泣くのが仕事だと知ってるなら、
(会社側は)泣いたらどんな対応をするのか。を具体的にしないとお母さんが安心して移動できないし、CAさんだって100%の力を出して働けない。知人の知人には、トラブルをおそれて搭乗前の子供に、軽い精神安定剤を飲ませる方もいる。
数席潰して(そりゃあ少しいろいろ高くなるかもですけど、そんなのぼくの考えることじゃない)赤さんとお母さん用防音シートは用意できないのかな、とか。
空を飛べるんだから、がんばんなさいよ経営陣。
インチキの源泉はだいたいヤワな精神論。
夏場の練習中に水飲んだらビンタ、みたいな。
べつに抗議でも問題提起でもないです。ひとつのインチキに気づいたら、
ぼくたちも同じインチキをしてないか。と、この店では話し合う。
そうすると、だいたい同じインチキをしている。だから、人様のインチキに気づくのか。
(ほんとうにごめんなさい)
世界最高のレストランは遥か遠い目標だけど、来店される方にとって良い夜にしてほしくてお店を開けています。具体的にこうしています。なんて、おこがましくてまるで書く気にはならないですけど。
明後日から雪まつりですね。新雪みたいにきれいに暮らせないからこそ。
【1/6(月)18:00より営業開始】
大晦日はひとりでNetflixでM-1をつけながら、switchのゲームを買ってきて格闘して飽きたところに年明けから1分過ぎて新年を知る。そして「ゲームもM-1も、僕にはもうテンポが速過ぎてよくわからないなー」と再確認してやめる。
触れていてどうも気持ちが良くない。翌日から2日ほど立て続けに人にお会いして年始のご挨拶を済ませ(すっかりご馳走になってしまった)そこから2日ほどまた家にこもった後に本屋に行くと『メンター(人の成長を支援する側)になるひと、老害になるひと』みたいな本を見て思わず笑ってしまう。
まるで、メンターが一切のセクハラをしない神みたいで、老害は、拾った財布は金に困って必ずネコババするみたいな悪者じゃないか。
好きだねえ。二者択一。「これを(いま)買わないと将来危ないぞ!」みたいな、脅しながらモノを売るのを罰する法律でも作れば良いのに。毎年、少しずつ仲間や身寄りが減っていく方を、聞いたふうな答えじみた仮説で脅し続ければ不安が増えて、そらやがて老害にでもなるでしょうよ。
—————————————————————
ひと月ほど前にとある居酒屋のお会計時にレジで並んでいると、そばのカウンター椅子に、店の制服を着た10代後半のアルバイト女子2人がクロックスを履いた両足をぱたぱたさせながら座っていた。スマホを眺めたまま、会計を済ませたお客さんが店を出るたび、ありがとーござーまーす、と声をかけている。どうやら、仕事が終わってレジ後ろにあるタイムカードを打刻したいが混雑が減るのを待っているとわかった。いろいろなご意見もおありかと思うが、しつけは僕の役目ではない。
彼女たちは、だれにもなんの気もつかってなくって(もう)仕事が終わったから気の抜けた挨拶に見えても(いちおう)仕事はする。その質はどうあれ(たぶん誰からも何も言われてないから)若い子が人目を気にせず制服姿でだらだらしているのは平和な気がした。それでも、つけまつげは、びっちりつけているのに、爪は短く切り揃えているなんて、おさえてるところはおさえていて素晴らしいじゃないか。と思う。なんだか、日本の未来は明るいな。このままいけよー。と微笑ましくなった。
言えなさそうなひとに、あまり言えないのは100歩譲ってわかるけど、
言えそうなひとにはがんがん言うなんてどうかしてるよ。
———————————————————
こうして、なんとなく息をひそめて暮らす日々が終わって、
またみなさまにお世話になる一年が始まります。現在1/5(日)19:39時点では仕事モードにはほぼ遠いのですが、明日1/6(月)18:00までには必ずなんとかします。
明日よりあらためてよろしくお願い申し上げます。
【1/1(水) きいちゃんと飲んだ】
年末に帰省してきたきいちゃんは中学の同級生で、水族館や、博物館といった建築をコンセプト面からデザインしている。昔のきいちゃんは、互いに10代の頃からかなり口が悪くて、僕のセンス(!)みたいなものは、君はアレだよね、いつもダサいよなー、とにこにこ笑いながらこちらのかすかな矜持を粉々に砕きまくる。
そんなもん読んで、
そんな音楽で喜んで
そんな映画で泣いて、
そんなことも知らないで、
それを良いというのか。
賛否両論ありましょうが、僕はずいぶん彼に鍛えられた。15年前の開店以前に「茶室をコンセプトにした店として…」と話してみたら
「やってるうちに飽きない?」とひと言で片付けられて目が覚めた。
危なかった。きっと3ヶ月で飽きた。ちょっとかっこいい感じは、心が粟立つほどあとでダサくなる。深夜に書いたラブレターを朝読むのと同じである。そんなふうにきいちゃんには毎回こちらの素敵と思うものは1秒で鼻で笑われてきたが、彼の言うことはいちいちごもっともだった。というか、僕の話すことは、いつも、どっかの誰かが話したこととまるで同じことであることによく気付かされた。
年月を経て、彼は柔和になったものの、この間の帰省でも、最近よく流れている音楽の、YもKもHもVも聴かないというので、理由を聞くと「うーん、外と戦ってる感じがしない音楽だからかなー」と言う。なるほど。僕も彼らは聴かないけれど、それはそう言う気分が自分の心の中にもあるな。と納得する。「自分の中でだけ完結しているだけだから、なんていうか興味がそそられない」とも話した。たしかに最近はこだわりや、見た目といった、インパクトの強いものが主流だもんな。と思う。
感動の頂点が、インパクトや意外性のある、驚かされるものである必要はない。小室哲哉に時代の遅れを自覚させた宇多田ヒカルのデビューだって、じわじわとヒットチャートを上がっていっただけで、インパクトではなかった。最終的に、15歳というデビュー年齢や、売上枚数が取り上げられてインパクトにすり替えられていったけど、実際のオリコンチャートで「オートマティック」は1位を取っていないもんな。みんなあの曲がラジオから流れてくるのを楽しみにしていて、なんかいい曲だなー。と言っていたのが始まりだから、良いものはいつも独り言のように始まる。そして、ぜったいに大衆を馬鹿にしないで寄り添う。
誰かの心に染み入るものを送り続けることがいかに難しく、忍耐と覚悟のいるものか。どんなことにも体が資本というけれど、知らない誰かの役にたっているかを確認する手段もまともにないまま、自分の心の深淵に糸1本垂らして、その時だけは仲間に頼らず手掛かりもなく戦い続けるには、「強さ」と「怒り」を自覚した「自然体」でいることが必要なのだと思う。
時代がインパクト主体になったのは「若い人向け」につくられた、このずいぶん頼りない世界に問題がある。でもそれは当たり前だけど「若い人たち」のせいなんかではない。若さからはみ出ることを恐れた「大人たち」がずいぶん長らく若い人に媚びて甘えたせいだ。
嫌われたくないことと意見を言わないことをハラスメント問題にすり替えながら、いつまでも「子ども部屋」からいっこうに出ていかないで居座ったからだ。その挙句、子ども部屋の中で若い人に対して隙を見つけて”私の若い頃”の話をしようとするか”吸収したがるふり”をしているせいだ。
でも、もう時は経ち過ぎていて、このスポンジには新しい水を吸収するにはぽろぽろすぎるから、僕たち大人は、痩せ我慢をしてでも知恵と経験と金を出して居心地の良い「茶室」を作ってそこの住人になった方が楽しい。
本当に自分の興味のある話を恥じらいながら互いに披露する場には、明確な気づきと、穏やかな感動が漂うと思うのです。
本年もよろしくお願い申し上げます。
【正しいことばかりしない】
うちのシェフに、焼きそば弁当が北海道限定なら、北海道料理ではないのか?という超屁理屈めいた話題(いつもどうでもいい思いつきに付き合ってくれてありがとう)になって、料理人が作る本気の焼きそば弁当を作ってもらった。
和寒の冬キャベツと道産小麦の麺を主体に肉は白老牛のシャトーブリアンである。冬キャベツもシャトーブリアンもこの時期だけにしか手に入らない。
これを大切なご接待の場に、ちゃんと(?)焼き弁の容器で出したら、すこしだけ緊張の続いていたように感じる笑い声がなごんだ気がしたけれど、ほんとうにそうであったなら良かったと思う。
こんなふうに、僕たちのしごとは、すこしだけお客様に立ち入るので、対お客様以外の人間関係やそれぞれの考え方というものにはあまり寄りつかなくなった。
たとえば、
町なかに熊がでて、それを撃つ猟師を悪く言うひとについてなにか言うとか、彼らの子育てはもう少しこうした方がいいとか、うちのお店にはシェフがいるから、僕は料理本を読まない。とかそういうことだ。先日、肉が食べられないお客様がいて、理由を聞いたら、ペット業界の闇、とか屠殺のしくみを知ってしまったから、と言う。だとすれば、もう一度肉を好きになってもらうようなことはしない。それは、そういった考えを持つ方への「ちょっとした批判」っぽいし、なにより説教くさい。説教は大切だけど、大切だからこそ、一度話したら責任が生まれる。僕はそんなにゆとりある暮らしをしていないからそんな大層なこともできない。だから肉を除いて気に入っていただけるお料理を提供するだけ、と考える。
批判してたら日が暮れる。しなくても日は暮れるけど。
批判はたいがいじぶんの心のありように向ける。そうするとそのうちだんだん自分の心に溜まる澱で自家中毒にかかって弱まってくるから、解毒に馬鹿げたことを考えはじめる。それが焼きそば弁当に姿を変える。
お客様の笑い声が聞こえる。ああ、やってみて良かったと思う。そして、馬鹿げたことに付き合っていただけるお客様やスタッフに感謝が生まれて、気持ちがすこし楽になる。
12/26(木)20:00〜12/29(日)まで焼きそば弁当をご用意します。
笑い納めにどうぞ。
【苺とアメトーク】
アメトークを観てると、いまを耀く芸人さんが駆け出しの頃の自身のVTRを観て悲鳴をあげている。もじもじして話すきっかけが掴めないとか、突拍子のないことをして引かれる、ただただスベる。未熟者だった頃の気恥ずかしさにくわえて、結局、過去の自分にアドバイスしたところで当時の自分は、どんなアドバイスも「うるさいわい」といって聞かなかったであろうことも知っている、そんな悲鳴。
お笑いも、音楽も、映画も、そしてもちろん一皿の料理も、世界は変えられない。かも知れない。
それでも、変えられない。なんて言ってとりくんではいけない。それを言ったらおしまい。だけど、僕を含めて、いろんなアドバイスをしてくるひとに耳を傾けなくていいし、恩も感じなくていいし、恩を感じられない自分に罪悪感も持つ必要もない。
うるさいなあと思っていい。
アドバイスより、シャンパーニュやサーロインをご馳走してくれるひとの話の方が耳に入ってくるよ。
世界を変えたい。という後ろ指をさされるほどの恥ずかしさが、じぶんとじぶんの暮らしを変えていく。
おっと、熱くなってしまった。
ディナーのあとには苺とシャンパーニュを。
大切なお相手とのひとときのためだけにご用意しております。
【未来の思い出話】
もともと自意識過剰なところではじめたSNSは自分をよりよく見せようという気持ちも強まり、本当に好きなものが言いづらくなって10年。そろそろもういいかと、すべての仕事をスタッフに押し付けてこの年末の忙しいさなかに、まさに「どうでもいい、何の役にも立たないこと」をすこし長く書きます。時間潰しに読まれる方は読んでください。
僕は、カップラーメンを食べます、ときどき。
以前、よく来ていただいたお客様から「カップラーメンは食べますか?」との問いに「年に数回、衝動に駆られていただきます」と答えたら、その日を境に来られなくなった。「こんな店(良店、というご好意でしょう)のご主人がカップラーメンなんて食べるんですか!」というのはきっとがっかりさせてしまったんだろうな。と申し訳なく思いながらもその後に付け加えた
「どん兵衛を30分寝かせてから食べます」という僕のおそろしい性癖の暴露も良くなかったのだろうし、今まで我慢させていた「なにかとの合わせ技一本」で夢の崩壊があったのかもしれない。先日、
私は今晩、私の時間が必要なの。
そう話す古くからの知人に呼び出されました。あまり書くと、迷惑がかかるかもなのでぼかして書きますが、知人は家人と暮らしの方向性でその日に衝突があったそうで家を飛び出した。そして、ワインを一杯だけ付き合って欲しいと、冒頭の誘いになったわけです。ぼうっとしてる僕のような人間には、ちょうど良いお役目なのでしょう。知人は(当然ワイン一杯では済まず)矛盾だらけの自己主張と家人への感謝と批判を波のようにくりかえしながらなめらかに酔っていきました。そして、
小野寺くん、あなたは私とキスしたいと思った時期があるでしょう?
と、言い出した。生憎、というかなんというか、前日のお酒が残っていた僕は、ゆっくり付き合っていたことで赤ワインを吹き出さずに済みましたし、だいたい、会ったのも久しぶりで、いったいどこの誰が「恋人でもなかった誰かとキスをしたい”時期”」があるんだろう。
そう思って黙ることにしました。
だいたい”あの時”じゃなくて”時期”って長くないですか?
そう、とにかく僕たちは(とくに知人は数杯多く)ワインを飲んでいましたから不倫について語り出す流れも自然でしたが、知人のそれは、すべて不倫を否定するものでした。そのときの店の主人と僕は、キスのくだりを聞いていたことで、まったく説得力のない否定話を、にやにやしながら聞いていたことは認めます。
ただ、ちょっと、ほんのすこし、
懐かしくなったんだろうな。と思うわけです。家におさまり、暮らしがセットされていく人生を、ちょっとイヤだな、と思ってしまう夜、そうやってすこし投げ気味に考えるときに、まだ痛みを知らなかった時期を、または傷の回復が早かった(と思い込んでいた)ころのことを懐かしく思う。
僕だって、最近よくラジオから流れる「Apt.(ブルーノマーズとロゼ)」を自由で未婚の僕が聞いたって、なんだかきらきらしている彼らとファンが羨ましいですもの。わかりやすくて覚えやすいフレーズを、暗くてもキラキラした空間で知らないひとたちと飛び跳ねながら大合唱していた時期がすこし懐かしいですもの。半紙を重ねるように過ごす毎日が、いつのまにかそこそこの厚みになっていて驚いて、鷲掴みにしても張りがなく、だらんと重たい書き損じの日々には、ほんとうに好きなものや好みだけが、暮らしていく強さをつくる。
そう思っていたって。
だから、日ごろから僕と(公私ともに)一緒に働いてくれたり動いてくれるひとたちには「嫌なもの、やりたくないことはハッキリ口にした方がいいよ」と話します。税金高くて払いたくないな、とかコンビニ弁当は嫌だ、部屋が狭いとか、冬が寒いとか、掃除機かけたくないとか、残業はもちろん仕事自体やりたくないとか。大小問わず。「仕方ない」なんて言わないで。咳が止まらなくて熱が下がらなくても、風邪だとわかれば対処があるように、もやもやした心にも名前がつけばやりようもある。
働き方を変えるとか、ほんだしでいいから手作り味噌汁つくるとか、遠くても広いところに引っ越すとか、ストーブをつけるとか、それから、愚痴ってすっきりしたいとか。そういう意味では、知人の対処策は素晴らしいな、と秋の終わりにひとり帰る道すがら思ったわけです。
帰りがけ、すこしだけ酔いの覚めた知人が言いました。「不倫願望がないと言えば嘘になる。でもね、したら終わり。家族が悲しむから」そして、こう続けました。
「不倫願望はね、未来の思い出話なの」
【12月の営業予定】
べつに、たとえば6月から7月に半年かわったところでそんなことは言わないのに1月を目前にした時だけ「今年もあとひと月か」と言ってるのはことしは、よく働いたからだと思います。
そういうことにします。
コンプライアンスだハラスメント防止だとかっこつけて世の流れに合わせてみたら、(いままでなにも合わせてこなかったので)休日もずっと社労士さんや弁護士さんにいろいろ訊いたり教えてもらって日が暮れた。思い返せばスタッフには
「ぼ、ぼ、ぼくと、お、お酒を飲みに…」みたいに仕事終わりの飲みニケーションへ誘ったし(死語)指示のすべては録音しました(うそ)年末のいいところは、こんなふうに振り返るには都合のよい区切り感があるところだと思う。
年齢を重ねていくと、古い知り合いとも共通のはなしはもちろんですが、思い出話ですら(今まで話し過ぎて)すり減って「あの話はどうなった?」みたいな話題がなくなってなめらかに【生存確認感】みたいな空気が入ってくるのも、
むかしとはちがう年末感があります。
いっぽうで、お客様をお迎えする仕事をしているとこの年末感は、あわただしさというよりもみなさんの【一息ついた感】がこちら側から眺めていて心地良いひと月でもあります。
先日、早めの忘年会みたいな、というより外側からはわからない、そして僕にはあまりに場違いな美しさの世界に潜入するみたいに紛れ込んでいたら主催者の方のひと言が、身体のあちこちにすりこまれたのでビボウ録としてもここに(そっと)置いておきます。
「一生なんて一瞬なんです。だから傷ついてる時間なんか1秒だってないんです」
【11/17(日)定休日に食べたりんご】
あまりこういうことは書かない(ようにもしてる)のですが。先日、若くて優秀な美術系のお仕事をしてる方から「とある友人が自分の仕事を批評してくるのが不快で何か言っちゃいそうになる」という話を受けた。
ぼくは、「そのご友人は同業、もしくはプロか」ということを訊くと、趣味でアート活動をしている。という話を聞いたので、だったらもう放っておけばいい。とこたえた。感性を使って仕事をしているひとは「こぼれる」からそういう仕事をするしかない。
非凡で優秀だから、ではない。
「こぼれる」先を受け止めるためにその仕事に就いたひとの一方で、アート活動している方に見受けられるのは、己の価値を探すとか高める、または、もうすこしつっこむなら、他者に自分の良さを認めさせるため。という匂いのするときがあります。両者には善悪の開きがある。のではなくてすでに住んでいる場所が違う。と思う。
冬は寒いからダウンを着たらいいよ。という助言も真冬のタイでは35℃である。
冬にもいろいろある。
そう。これは覚悟の話。
感性で仕事をしているひとが素晴らしく、毎日決まった時間に決まったことをするひとはどうか。という話ではないです。ただただ、
好 き な ほ う を 選 ん だ ら い い
と思う。そう書くと(選べない事情のひともいる)という人が最近いるらしいのですが、では、昨日食べた1個のチロルチョコの美味しさを語るだけで、世界中の甘いものを同時に語らないとチロルチョコの話はできないのだろうか。いま、選べない事情のひとのことは話さない。ぼくも含めて、ぼくたちは、ちょっとしゃべるときに、注力して話すことはだいたい主観が強くて、データなんかとってないし、まとまっていなくて、論理に穴が多くて、なにかを踏みつけていたりするくせに最後はけっこうこう話す。
「みんな言ってるよ」みんな。みんなってだれだ?って自分で思いながら。
良くない。ことをあげるとすれば、
それは、ずけずけと感想をいう感性だと思う。
そう話すひとと会うと「ちょっとご自分のことが好きじゃない時期なのかな?」と感じる。良い。という反対、つまり、悪い。ということばを排出するとき、それは言われた側の支持者や、時に購買者を同時に批判することにもなりかねない。だから、ひとや何かを「悪い」と、ちょっというときって、ちょっといわない方がいいと思う。丁寧に、相手とその関わり合いのすべてをつぶす覚悟とか義務があるし、それをしっかりこなしたとて、しっかり恨まれるのだから。
わたしは、あなたも、あなたのみのまわりもみとめません。というふうに。
今朝食べたりんごはとても甘くてつまんだ指先がすぐにベトベトして、
ぼんやりしたあたまもひと口で目が覚めた。そういう甘さにうっとりして、
好みの暮らしを思い出して、きのうまでにあったことを落ち着かせるために、
日曜の朝があるのではないかと思っています。
明日は雪ですってよ、奥さま。
【夜の焚き火】
いまから6年ほど前、冬の山中でひとり、薪をかついで秋刀魚と鶏肉を持って焚き火をしたことがあります。面倒だから、塩だけしてホイルで包んだ食材を燃え盛る薪に放り込んで、ぼんやりしていると耳全体が軽くなっていきました。
暮らしているだけで、肩同様、知らないうちに耳も凝ってくるんだな。
その時から思うようになりました。薪が小さく爆ぜるたびに、伝わる夜のしじまが耳全体に染み込んで疲れがとれていく。なんの音も入ってこない耳は、きっと、薪火に紅くてらてらと照らされていて、
そこだけ体温も上げていく。
しかし、そこは熊でも出たら「およそ一撃」な場所。
だから、鹿が突然、首をもたげて警戒するみたいに
心は、あらゆる森の命を警戒している。下手をすれば死と紙一重であるのに、
誰かといるより楽な夜は、亡くなったひとや、飼っていたねこたちが、いったい今ごろどこに暮らしているのか。——みたいなことを連想するのにたやすい。
家とか会社の机の引き出しを開けるとみんな、生きていたときの体が、お米くらいに小さくなって、そこに彼らの住む小さな町や村があって、たのしく暮らしていたらいいな。と思う。穏やかに。安らかに。だけでなく、
ちゃんといらいらしたり、夏にコーラを飲んだり、飴くらいの優しい言葉をかけたりかけてもらったりしていたらいいな。と思う。
話しかけることはできないけどルーペでみると、当時のねこが、ほかのきょうだい猫と陰陽みたいにまん丸くひっついて寝ていて、祖母はあいかわらず祖父に小言をいっていて、ともだちは季節の良い川っぺりあたりで自慢の男臭い車を自撮りしながら、今じゃもう珍しい煙タバコを吸ってるんではないかと思う。
魂だけが、ほかの世界を覗けると思うなよ。
【彼はシーフードを食べないの】
My son doesn’t like seafood.
韓国からいただいた、ご家族でのコース予約内のリクエスト部分に、そう書いてありました。私たちのお店の場合、ふた品目にお刺身を出すので
(では、どうしようかな)と頭が働きかけると、つづけて、ご両親(祖父母)とご自分たちの年代が書いてあって最後に、こう書いてある。
He is 14 years old (puberty).
「息子は14歳で(思春期)なの」とあって、微笑ましく読みました。
がんばれ。と言われても腹が立って、なにも言われなくても腹が立った、あの時期のことか。
もし、塗料スプレーを渡せば壁に汚い言葉を描いて、整髪料を3日で使い切るほど髪をこねくりまわす、あの時期のことで、人生でいちばん舌打ちの音が綺麗に出せて、「こんにちは」「おねがいします」「ありがとう」そういった、あらゆる挨拶をなぜか忘れてしまうあの時期のことだ。時どき、思春期のみならず、暮らしにもがくひとに「まだいろいろ可能性はあるね」と話すおとながいますが、
僕はそれをきくたびにすこしだけ「ごうまんだなあ」と思ってしまう。
14歳には14歳の国があって、その中で頑張って暮らしている。
具体的ではないとしても、もがいている。まだ子どもの彼には、もがいていることだって、頑張っていることのひとつだ。
貧乏な国で、我が子へたったひとつパンすら満足に与えられず苦しむ母親に「まだいろいろ可能性はあるね」とはぼくには言えない。
平和な日本に居たって、ひどく歪んだ悪意にふれて、志が変形することもある。勘のいい子どもなら、
そういう事態をすでに感じとって、ひとり勝手に慄いているかもしれない。
だから、「パン」を具体的に差し出せないのであれば
経験者は、黙っているしかない。子どもは、かならずそういう人間を見わけている。見わけていなくても血管が透けるほど薄い、その新鮮な皮膚で信用に足る人間を確実に嗅ぎとっている。
だから(ほんとうにこちらからは伝えたりはしないんだけども)口ごたえしてきても良いし、むすっとさせたら申し訳ないけども、「がんばれよ」と言いたくなる。正確には「おとなの世界へようこそ」と、ひっそりと、ふすまの奥から勝手に応援している。
おとなの世界は、孤独との闘いである。
己のなかに生まれる、かすかな違和感にむきあい、他者への礼儀を忘れてはならず、自分自身のストレスで自家中毒にかかって生まれた寂しさを、他者に癒してもらいながらありがたいと思いつつも、そのしがらみから離れることをひっそり願う日々。孤独を好んで、孤独を嫌う日々。
自分からは逃げられない。それを受け入れる年月。
「おまえもがんばれよ」と、彼がもしそう返してきたら
今が旬のいくら丼くらいは大盛りでご馳走する。
あ、そうか。シーフードが嫌いだったな。
やっぱり、ひとがひとにできることは少ない。
【経験したいこと】
さいきんはずいぶんシケた暮らしをしています。
旅行には行けないし、本は読み切らないし、人の話はちゃんと聞いてないし、
急ぎ足で、すれ違ういぬと目線だけかわして、眼鏡を拭かないままじぶんの健康を気にしている。こうなってくると、誰かがこっそり大切にしているなにかを知らない間に踏んづけたりしたかもしれない。
いや、そう思いつくんだからきっと踏んづけたんだろうな。
この場所に言い訳も置いておく。
今年が終わっていく。誰かが(おそらく)本当に話したいことのかわりにスポーツとか、政治とか、目立った話題で世相をまとめながら一年を振り返る。
時の流れが早いと、嘆き気味に話す。
だれとも競争しない生き方をえらんで49年が経つ。うまくいかない状況も、
もっとうまくいかない状況から見れば、すこしうまくいっている。
反対に、うまくいっていることももっとうまくいくやり方があったかもしれない。
いまは少しシケていても、流れの一部でしかないから悲観もしない。方がいい。
土砂が流れて清流に還っていけば、
野生のイノシシを食べてみたい。
南紀の白浜をながめたい。
地面師たちを何回も観た人とお酒を飲みたい。
圧倒的な星空の下、焚き火をしたい。
増毛のシャインマスカットの甘さを若いひとに伝えたい。
伊丹十三記念館に行きたい。
焼きたてのパンの香りでわくわくしたい。
スナックラジオのくだらなさを大切にしたい。
親に長生きしてほしい。
お金に物を言わせない、新しい価値観を待っている。
【10/20(日)定休日】
貧乏と貧乏性はちがいますね。
ふうふと内縁関係くらいちがいますか。
いや、ちがうか。
ふうふと内縁関係にはたがいに抱え合うものがある気がするけど、
貧乏なお金持ちはいなくても貧乏性な人は、お金持ちにもいるものな。
朝から、届いたネット購入の冬服たちをならべて、軽くサイズを確認してからタグを切って、捨てて、包んでいた段ボールたちを畳んでみると、この1カ月でかなり大きくまとまってきたので、ずりずりとマンションの地下まで捨てにいって、昼以降に食べる蒸し野菜を下ごしらえして、朝方の寒さに着込んで買いに行ったサンドイッチを牛乳でたべながら、1週間の情報番組をかけっぱなしで事務仕事をこなしてたらうとうとして、シソンヌのコントをかけっぱなしで眠って、起きてザ・ノンフィクション見てたら、あっという間に時間がすぎていることにあわてて髪を切りにいってから、運動も兼ねて徒歩でハンドソープを買いに行く。
行ったついでに、気になるエッセイを2冊買って
「今日はこれくらいで勘弁してやるか」と、ひと息つこうとしたところで、昨日、よく伺うカフェに、財布を忘れてお会計を失礼していたことを思いだして、あわてて車で向かって、コーヒーをいただきながら、
「あ、任天堂switchのソフトが届いてたんだった」と思い出す。
ゲームなんて有料で手にしないのに。
今日は、これからビールを飲むかどうかも決めなくてはいけないし、下ごしらえの蒸し野菜にも火を入れないといけないし、趣味の調べものは途中だし、買ったエッセイは気になるし、最近もやもやすることが、どうして今でももやもやするのか考えなくてはいけないし、今朝見た夢も検索しなくてはいけないし、手紙も、返信していないLINEもあるんだった。
それらが終わったら、世界中の犬や猫たちを、
ソファやなにか、いつも柔らかく暖かい場所でいつまでもゆっくり安眠させるためにはなにができるかを考えなくてはいけないんだった。
仕事をしてる暇などないんだった。
【10/16(水)思い出】
「人生をドラマティックにしない」というのが座右の銘です。と言いながら
ずいぶん不思議なことが起きます。生まれてすぐに難病の強い疑いからはじまり、子供の頃から、そこそこ多数の友人を亡くすといった経験、失恋した瞬間に初雪が降るというような新しい春がくれば忘れるような程度のもの、はたまた、ロンドンの交差点で札幌では美人で有名な同級生にばったり会うとか、街なかで1000万の入った鞄を拾うというような、
まあそういうことです。
ただ、喪失の出来事は都度、経過と理由と悲しみの質がちがいましたし、難病の疑いなど、産み落とされた直後の赤子に思うことはありません。
失恋も、いつの冬にも必ず降る初日と重なったタイミングで、いつぞやの美人な同級生とも、なにも起きずに30年が経って拾った鞄は交番に届けて、貯金はありません。
これらの素材に、過度な味つけをしてドラマティックにすれば、もともとの風味が損なわれる気がするんですね。驚きや悲しみ、ときには喜びも積極的な共有をできるだけ避けて、ひとり勝手に熟成していくものだけを思い出と呼ぶようにしています。
【10/14(月)おとなのはなし1】
「子育てはもうね、ほんとうにたいへん」笑顔でそう話すのを、静かに聞いていたひとには事情があって、子どもが産めないのでした。その微笑みは、この季節の陽が差し込む部屋と同じ温度。
また、そのむかし、海外で長く働いていた友人が
「帰国する前の晩に、仕方なく上司と寝てきたの」と今はもうない居酒屋で、ひさびさの日本酒に酔って口がすべる。
「上司には恋愛感情があって、私には感謝や尊敬しかなくて、もう自分をふくめていろいろ残念だけど仕方ないかって」
蟻にも象にも、きっと、事情はあってただその事情をまとめるときの
あの「ちいさな軋轢」をきらって生まれる”やり過ごす”というわざには思いやりだけでなく、あきらめまじりの覚悟がまざっていたのでした。
秋が深まります。
【ふゆのはなし】
つかれているひとが、冬囲いの話をしながら「どうやら僕は何者にもなれそうにないから」と家を買うことにしたようです。なにをきっかけに何者にもなれないと思ったのか。ということと、家を買うことにどんな関係があるかを訊ねることはややしばらく考えてやめました。
つかれているときは、自分がかつて、おもらしをしたことを知っているような血のつながりのあるひとと過ごすといいです。と書いた今日は敬老の日。
太陽は沈む直前でも眩しい。
【9/15-16(日月)連休のお知らせ】
森の傍に流れる川の水はなぜ、地下に吸いこまれないのか。
そういうことを考えながら暮らしているわけです。
けっこう笑われるのですがいちど気になってしまうとそのことばかり考えています。
そうしてこたえが見つかると、今度は黄葉を数枚見つけて秋のはじまりを札幌で最初にみつけたひと。という設定でひとり、コーヒーを飲みに行きます。
連休もきっとそのように過ごします。
どうぞみなさま素敵な秋の日々をお過ごしください。
【架空の格言と日曜営業のお知らせ】
お世話になっております。9/29(日)は営業いたします。ふだん来れない方もお酒だけの方も気軽にいらしてください。お待ちしております。
『酒がすべてを忘れさせてくれる。というのは迷信だ。
空き瓶を前に”もう一杯だけ”という欲には無力なのだから』
——アル・カポネ(嘘)
【架空の格言と9/1(日)定休日】
夏のまま秋を迎えた今日。
目線をすこし上げると遠くに雪景色が浮かびます。今月は一度ですが9/29に日曜営業もいたします。皆さまのお越しをお待ちしております。
『愛情は、寂しさからも発生する。
それに気付かず愛し始めると、寂しさは増す』
——ヘミングウェイ(嘘)
【架空の格言と8/25(日)定休日】
こんにちは。
あたたかな陽射しのなかに秋がまぎれこんでいます。
新たな季節のはじまりに、物想いに耽ってみます。
お休みの方もお仕事の方も素敵な日曜をお過ごし下さい。
『頭が良いからといって、賢いわけでない』
——ソクラテス(嘘)
【架空の格言と8/18(日)定休日】
ご好評いただいておりますのはシャサーニュ・モンラッシェの赤です。白ワインの銘醸地ですが、赤ワインも偽りなく素晴らしいです。
台風一過の日曜が良い一日になりますよう。偽りといえば。
――――――――――――――――
5歳の私は
口紅なんて使ってないわ。と真っ赤な唇で母を困らせ
17歳の私は
女友達と出かける。と父を安心させ
35歳の私は
愛しているのは夫だけ。と世をあざむいた。
偽りだらけの人生どおり
私は、死ぬまで極上の嘘で民衆を酔わせる。
――ブリジット・バルドー(嘘)
【架空の格言、そしてお盆でございます】
こんにちは。
お盆期間では当日にお席の用意が叶わずご迷惑をおかけしております。
暑いですから事前にお電話されることをおすすめしております。
お手間かけます。
On ne prend pas de poids parce qu’on a pris une bouchée d’un superbe jambon mariné au fine . On prend déjà du poids quand on pense qu’on peut en prendre une bouchée.
‘’フィーヌに漬け込んだ極上のハムを一口食べたから太るのではない。
一口食べようと思った時点ですでに太っているのだ”
――フランスの古いことわざ(嘘)
【8/11(日)定休日】
自宅ちかくの道を歩いていた土曜日の夕方犬が降ってきたことがあります。
今から28年前、東京住まいのころ、どうやら、それは3階建の町寿司の屋上、
犬は柵のすきまから転落したようでした。犬は、停めてあった自転車のサドルに跳ねた瞬間だけ悲鳴をあげ、地面でふたたび跳ねました。
子どもの頃から、ぼくの暮らしにはときどき不思議なことが起きて
それはいろどり、みたいなものを添えてくれるのですがそのときはさすがに頭のなかがまっしろになり、寿司屋に飛び込むと威勢のいい大将に迎えられるなか
「あの、犬が降ってきたんですけど」と伝えると不穏な空気。
「あの、犬を飼ってませんか?」の問いに数秒を要して
サンダルばきのおかみさんらしき女性が突然
「ポチ(仮名)!!」と叫んでぼくを押し退け犬の名を絶叫します。
ぼくはいたたまれなさと怖さの混じった気持ちで地に落ちた犬を見ることなくその場を立ち去りました。そのころのぼくといったら、どこか人生を投げやりに暮らしていましたから犬に、どこかじぶんを重ねたのかも知れません。
家に着いても犬の短い悲鳴は頭の中で鳴ります。それはじぶんの暮らしが、目標や理想とはかけ離れているぞ。というサイレンのようにも感じました。
翌日の日曜日も一日中あたまの中で鳴り止みません。ひとと話すのは億劫な時代でしたが、仕方ありません。意を決して月曜の仕事帰り、寿司屋さんに伺いました。注文できる暮らしではなかったので気がひけます。カラカラと引き戸を開けて威勢のいい挨拶に負けないように「犬はどうでしたか」と訊くと、奥からおかみさんが出てきて「先日はありがとうございました」
と言って前掛けで両手を拭きながら「前肩を折っていたんですけどそれ以外は無事でした」と安堵のまじった笑顔でお礼を伝えてきました。
帰り道には缶ビールを買って、酒屋から出てたばこに火をつけるとピース独特の甘い香りが心を鎮めます。そこでようやくサイレンは止みました。
【8/4(日)定休日】
誰かと、意見や好みがまるで違うとき。「あのひとは、私を安心させたり楽しませるために生きてるわけではないもんね」と話す人が素敵です。
ただ、「確かにそうだよ、そうだけどさー、なんかさー」というひとの素直さにも惹かれますね。
【架空の格言とめおとおなら】
友人に、おならする夫婦がいます。まあ、みなさんしますけどその夫婦のあいだでは、おならもげっぷも(うちの中でだけ)一日中じゆうにします。さしいれのビールをのんで、げふっ。
美味しい手料理をたべながら、ぷう。
「だって我慢してたら体にわるいでしょう」
と妻が言い、夫がぷう。返事か。
みなさんにはひとおなら、もといひと息つく場所はありますか。
昨日いらしていただきましたお客さま、
あらためてご結婚おめでとうございます。
たくさんおならしてくださいね。
最後に
「美しい言葉も、げっぷする同じ口から出る」
——ハンガリーの古いことわざ(嘘)
【7/28(日)定休日】
僕にとって、肉食動物が草食動物を狩る画像を見たくないのは、
たやすく草食動物に肩入れする自分の浅はかさに気づくのが嫌だからです。
さて、これからステーキを食べてきます。
お休みの方もそうではない方も良い日曜日を。
【花と傲慢】
犬を蹴って、たべものを捨て、日々もがいている人を嗤って、
じぶんの好みでひとを縛る。
というよりも
しょげたふりをしながら長財布に伸びる指先を盗み見たり、
てきとうなお土産を満面の笑みで渡したり哭くひとを慰めて悦に入る。
そして、それっぽいタイトルで駄文の帳尻を合わせる。
こういうほうが傲慢かなと。
本日日曜は定休日。
また明日7/15月曜日よりお願いいたします。
【いいちこみたい】
運転中の流れる景色に紛れて
お母さんに駄々をこねる浴衣の女の子。
その泣き声もドップラー効果を帯びて
うしろに飛んでいきまして。
いつか、彼女がお祭りに向かうさなかに道端で泣いた今日の記憶も、
遠くなれば、今度はじぶんの子を膝のあたりであやしつける日にうつろうのかもしれません。
酢橘蕎麦の季節も巡ってきました。
なんだか、いいちこみたい。
【B級の暮らし】
茄子がやけに美味しかったり、日曜の昼下がり、
再再再放送の映画を寝そべって観たり、
気温は悪くないのに曇天模様であったり、
温めていたはなしの反応がいまいちだったり、
ディナーの約束がランチに格下げになったり、
信号がだいたい黄色だったり、
定番の味以外はすべてそろっていたり。
大きく厭なことが何ひとつおきない暮らし。
本日定休日です。
明日よりまた情熱ひとつ、用意がございます。
【げんきのでない日】
悪口を読まないで、聞かないで、
お酒を飲まないで、
積極的に笑おうともせず、
そんなじぶんをせめず、
頭を働かせるような映画や本をよけて、
なるべく日向に身をよせて、
あいさつくらいはきちんとする。
この間の相談にうまくこたえられず連絡先も伺わなかったので
こちらに書きおきしておきます。
おやつはいつもの戸棚にあります。
- 過去の日記やHAC機内誌に連載しております
「和食店主の不親切呑み歩き案内」はこちらに随時更新しております。
●HACボツエッセイ
不親切案内
「友人とシュークルートを食べる」
店は、西陽が似合う雑居ビルにある。
さいきん、若い女優と不倫をはじめた。と話す友人とふたりで食事をすることになった。このエッセイの話がきたとき、書いてみればいい。面白いものが書ける。と彼の言葉が後押しとなり、3年以上も続けてこられた、借りに近い思いを抱く古い付き合いだった。
里帰りした札幌には情報がないというので、私が予約したフレンチである。
レストランにつづく三条通りには、銀杏並木の絨毯が、急ぐ足並みにまとわりつく。初秋の風はすぐに肌を乾かし、あの暑さの記憶をすべて消す。
ビルの2階に上がれば、どこか古い図書館の風情を忍ばせた木の床が広がる店内の奥、街路に面した窓に差し込む緑黄の逆光を背負った男がこちらを認めて手を挙げた。
古いヴィンテージのシャンパーニュで乾杯をすると「女房と離婚してその女優と再婚しろって言うんだよな、親父もおふくろも。」と友人が言った。彼は名家の長男で、血筋に議員や医者が占め、結婚すれば跡取りをごく自然に求められる家系であったが、それがスムーズにいかなかった。奥さんが途中で罹った病の薬で産めない身体となった。
両親がその不満を隠さなかったことで彼の妻とは何年も会っていなかったはずである。
昨夏、彼の仕事都合で夏休みがずれ、妻側の里帰りについていなかった隙に、友人は、若い女との関係に弾みをつけた。それが冒頭の不倫相手である。それを今回、実家で話した結果が先の両親の言葉となった。
息子の不貞を責めるより、両親は目を輝かせて血筋の義務を果たす提案をやめなかった。
相当額の慰謝料の提案も具体的にしてきた、と友人は話しながら、舞台メイクで首から背中までタトゥーの入った愛人の写真を私に見せて笑う。
どうするつもりだ?と尋ねる選択肢を持ち合わせていない私は、届けられた前菜を2人分に取り分け、去年リリースのサンセールとともに口にする。ワインの蜜香は弱く味わいも軽いが、初秋とはいえまだ麗らかな気候には、溌剌とした酸味が食欲をそそる。
いつも元気でかわいいんだよなあ。と、スマートフォンをのぞき込みながら目を細め、喉仏を上下させながら白ワインをごくごく飲んで「選択肢はいつもこちらにあった方が楽しいよな」と話す。
シュークルートが運ばれてくる。
豚のソーセージと豚のコンフィが鍋の中で存在を示す。重そうですらある。
豚肉がこうも旨味を引き出されるものか。
はち切れんばかりのソーセージと、時間をかけて仕込まれた柔らかい肉。
古いシャンパーニュと、若いワイン。
女房と、26歳の愛人。
わたしの頭が何かを言おうと画策している。しかし、友人が、おのれの欲望に従った以上、正論の中にこたえはない。別れ際、友人は「今度、札幌に連れてくるからよ」と言ったが、どちらの女のことを指しているかは聞かなかった。
翌日、自転車に乗っていると、夕焼けのはじまりの歩道の上に、カラスがたかるふっくらとした山があった。それは陽をふくんで白銀に輝く美しい鳩の羽毛のすべてであり、その中にカラスにつつかれ死んだ鳩の赤い死骸があった。
あるがままの死と生の繰り返しを見て気づく。
夏の暑さも、過ぎてしまえば忘れる。友人の言動、奥さんの思い、若い女優の誇らしげな笑みも、名家の画策ごとも、いつかきっとなにもおぼえてはいない。
なにより、いまの私や、私の暮らしにはまるで関係がない。
ただ静かに時が過ぎるのを待てばよい。
あなたがなにかを言ってくれるはずである。
今回の不親切案内
「H」
狸小路とノルベサの間のセブンイレブン角から西陽を頼り、そこから見える雑居ビル2階。
【HAC 冬号 エッセイ】
「会員制のバーで飲む、または厳冬奇譚」
連日の誘いを断らなかったバチが当たって、数杯でしこたま酔った夜のことでした。よせば良いのが此の夜は、格好をつけて飲むときに行くと決めている会員制のバーの扉を二軒目として開けました。こぢんまりとしたL字のカウンターをなぞり、ひとり一番奥の席に着く。赤褐色の壁、額におさまる花写真、闇に溶けた10席に満たない間。
大先輩である店主が、どうしますか。とシャンパーニュボトルをさりげなくこちらに向けるのを受け、両手でおしぼりを揉みながら一杯お願いします、宜しければお付き合いください。と促し、主人と乾杯をした時に気づいた。客は私と、それぞれひとり客が2組。
ひとりは、店の真ん中あたりタートルネックとハリスツィードのジャケットの品良い紳士が紫雲をくゆらせ、ピノノワールと思しき赤ワインを飲んでいる。
そして、私から見ていちばん奥、つまりカウンター正反対に、酔い腐れた視力と暗さでいまひとつわからないものの、柔らかなオフホワイトのブラウスを着た女性客がいた。たおやかな長い髪が、うつむく横顔のさまと良く合って見え、私は己の歪んだ姿勢を糺して喉奥で小さな咳をする。
不意に紳士と目があう。父親以上の歳である。「不思議な話があるんで聞いてチョウよ」
そう話しかけられる。あるじが酔客の語り口を止めない時は、信用の証である。こちらも弛んだ笑顔を作り、伺いはじめる。
「ワシは親父の代から洋品店の卸を営んで居ります」洒落た風貌に合点がいく。「バブルの時は仕入れた服に値札を貼る前にぜんぶ売れてしまうもんで、当然調子に乗って稼いだ金はぜんぶ酒と女と馬にくれてやったデよ」
微笑む店主に赤ワインを注ぎ足された紳士は、ステムをつまみながら「そらあ店は傾くでショウ」と笑う。「数年は辛い思いデよ、値付けの上げ下げから、仕入れや人減らしまでなんでもやるでショウ」
私は、紳士の語りに頷きながらも、端で佇む女と、目でも合わないものかと密かに期待している。
「結局ワシは、サボった歳月の倍以上、身を粉にして働く以外、立て直す道はなかったってことデよ。でも1週間ほど前、むかしから世話になっている顧客の大女将に会って不思議なこと言われたデよ。うちは住処と店舗が一体になっているもんで、その入り口のシャッターに、夜になると、白黒の忌中の貼紙がされていたことがあるって話すでショウ、ワシ、そらあずいぶん驚いて」
え。と思わず声が出た。いつのことですか?と尋ねる。
「それ、いくら頑張っても商いが真っ赤っかの時期のことデよ。毎晩ずうっと貼ってあったっていうんだわ。もちろん葬式なんて出してないでショウ。しかもこっちはそこに住んでるわけで、出かけて夜帰る時も入り口開けて通るわけだでも、一度もそんなもんみたことなんかないデよ。だけどお客さんみいんな数年のあいだ、気味悪がって近寄らなかったってハナシ」
紳士とふたり、そのからくりに幾つかの仮説を立て盛り上がった後、彼はタクシーの手配を店に頼んだ。北の道は凍結している。到着後、私は彼に付き添い、タクシーまで見送る。そして己の足取りのひどさから自らも尻もちをついた。そろそろ撤退した方が良さそうだ。ようやくあきらめがつきつつも、くだらない未練が残る。
女性客に挨拶くらいはして帰りたい。
店の扉を開けるにひとしく、あるじが出てきて手刀を切り「トイレ。店番よろしく」小ぶりな店内にはない、ビル共用のそこに向かう。
微かな機会。私は、女性客にまるで興味のないそぶりで席につくあいだ、ちらりと目配せをする。そして目を張った。心は、底まで凍りついた。
女は老婆であった。オフホワイトのブラウスは正絹の死装束であった。縦結びの帯で右上前に重ね合わせられていた。うなじより低い位置に一本に束ねた白髪、深い皺に包まれた横顔は、うす闇のなか、もの憂げにおし黙る。
そこまで。ーーそこまで。
のちのことは、どう帰ったかも含め、
なにひとつ思い出せずにいる。
本日の不親切案内。
すすきのに入る手前の通りにあるビル一階「T」※会員制
【HAC機内誌初夏号】
「ドイツ製のジンを飲む」
陽射しに角度がついて、静かに初夏のはじまりを告げる夕方でした。
気に入っているシャツが受ける風で、すこし気持ちが保たれて、いつも混んでいる馴染みのバーに連絡もせずに寄ってみるとすんなり通される。そういえば、と、日中の赤信号にもあまり捕まらないでいたことを思い出す。
席についてジンを頼むと小さく品の良いグラスに注がれる。
お早いお越しですね。
とマスターより尋ねられるのを、そうですね。
とだけこたえ、今日はちょっと内内のことで臨時休にしたという事情は話さずにちびりとやった。
この、ドイツ製のジンは食道から胃を通るあいだ、冷たくも熱くも感じられ、風味がうつくしいと思って飲んでいる。気持ちがおちつく。
こんなに素晴らしい雰囲気を、本誌のこの連載にでも、と思って勝手に文にして読み返すとどうも心もとない。おさまりのわるい流れと貧相な表現が目につく鼻につく。
きっと素人手腕の問題だけではないだろうと思っていたら、手厳しいと評判の編集をこなす友人が指摘をしてくれた。
きみの文章には人に寄りそう感じがないからな。言っちゃあ悪いけれど、人間の弱いところをみつめて許す幅を持っていない人柄が露呈しているもんなあ。ハハハ。
なるほど。と、平静のふりをしつつ合点がいく。と言うよりも本当は返す言葉が浮かばない。
確かにそうなのだった。私は私のことをすっかり棚に上げきって、しかもそこから人様に指を差しながら正しいことばかりを話している。嫌な気持ちになると、自分のせいにするのは申し訳ていど、あとは誰かのせいにする癖が治らない。酒に飲まれる人間はきらいなくせに、自身には思い出さないよう、心を塞いだ夜がある。
若い頃、東京に暮らしていたことがある。
あの街で人生初の賞与をもらった勢いで当時気に入っていた女性と青山のバーに行った。
泡だ白だの赤だのなんだと、ワインを痛飲してしこたま酔った勢いで、同じ並びのカウンターで、5席も離れた常連と思しき紳士に赤ワインを引っかけてしまった。正確には、彼によく似合う(だろうはずの)椅子にかけていた白い麻のジャケットに、だった。本来なら届くはずの距離ではない。
私は、置こうとしたグラスを誤って倒す刹那、勢いよく手を伸ばして転倒を防ごうとした。それがすべて良くなかった。私の指は(それは見事に)グラスの脚を払う所作となり、大ぶりのリーデルグラスは弧を描き、真紅の液体を虚空に吐き出しながらジャケットに接地し、堕ち、粉々に砕けた。
その音が合図のように、これほど人が居たのかと思うほど、火事場を納めるスタッフが店の奥から出てきてジャケットに駆け寄ったものの、誰の目に見ても真夏の一張羅は、血塗れの即死であった。謝るマスターに紳士は、いいからいいから。と言って微笑んでいた。
呆然とその場に凍りつきながら私はいまだなんらかの体裁を保とうしていた。つまりそれはどうにかして時を戻そうと言う相談に等しかった。私は当時からその程度の男なのである。ようやく、いちばんのそれは、謝罪であることに気づき被害者へ近寄り、こう言った。
もうするわけあるません。
発した言葉の不出来に、店内に空っ風が吹いた。それから紳士の品格ある口髭が小さく動いた。「次にやったら怒りますよ」
あのとき誘った女性のことを、私は恥と未練と共に覚えているが、彼女は私の名前すら覚えていないだろう。
あの季節から25年ほど過ぎて今、自分の人間の幅はいかばかりかと思う。いっそのこと、このお気に入りのTシャツを誰か汚してはくれまいか。そのとき私は何と言うのか。
この店は、その答えをさぐる時間をくれるバーである。と書けば格好はいいが、これは正確ではない。何ぴとにも寄り添ってくれるバーなのである。
今回の不親切案内
バーR
すすきの交差点から北西に徒歩3分、大きなオブジェがあるビル10階
日曜休
【HAC機内誌冬号】
「会員制のバーで飲む、または厳冬奇譚」
連日の誘いを断らなかったバチが当たって、数杯でしこたま酔った夜のことでした。よせば良いのが此の夜は、格好をつけて飲むときに行くと決めている会員制のバーの扉を二軒目として開けました。こぢんまりとしたL字のカウンターをなぞり、ひとり一番奥の席に着く。赤褐色の壁、額におさまる花写真、闇に溶けた10席に満たない間。
大先輩である店主が、どうしますか。とシャンパーニュボトルをさりげなくこちらに向けるのを受け、両手でおしぼりを揉みながら一杯お願いします、宜しければお付き合いください。と促し、主人と乾杯をした時に気づいた。客は私と、それぞれひとり客が2組。
ひとりは、店の真ん中あたりタートルネックとハリスツィードのジャケットの品良い紳士が紫雲をくゆらせ、ピノノワールと思しき赤ワインを飲んでいる。
そして、私から見ていちばん奥、つまりカウンター正反対に、酔い腐れた視力と暗さでいまひとつわからないものの、柔らかなオフホワイトのブラウスを着た女性客がいた。たおやかな長い髪が、うつむく横顔のさまと良く合って見え、私は己の歪んだ姿勢を糺して喉奥で小さな咳をする。
不意に紳士と目があう。父親以上の歳である。「不思議な話があるんで聞いてチョウよ」
そう話しかけられる。あるじが酔客の語り口を止めない時は、信用の証である。こちらも弛んだ笑顔を作り、伺いはじめる。
「ワシは親父の代から洋品店の卸を営んで居ります」洒落た風貌に合点がいく。「バブルの時は仕入れた服に値札を貼る前にぜんぶ売れてしまうもんで、当然調子に乗って稼いだ金はぜんぶ酒と女と馬にくれてやったデよ」
微笑む店主に赤ワインを注ぎ足された紳士は、ステムをつまみながら「そらあ店は傾くでショウ」と笑う。「数年は辛い思いデよ、値付けの上げ下げから、仕入れや人減らしまでなんでもやるでショウ」
私は、紳士の語りに頷きながらも、端で佇む女と、目でも合わないかと密かに期待している。
「結局ワシは、サボった歳月の倍以上、身を粉にして働く以外、立て直す道はなかったってことデよ。でも1週間ほど前、むかしから世話になっている顧客の大女将に会って不思議なこと言われたデよ。うちは住処と店舗が一体になっているもんで、その入り口のシャッターに、夜になると、白黒の忌中の貼紙がされていたことがあるって話すでショウ、ワシ、そらあずいぶん驚いて」
え。と思わず声が出た。いつのことですか?と尋ねる。
「それ、いくら頑張っても商いが真っ赤っかの時期のことデよ。毎晩ずうっと貼ってあったっていうんだわ。もちろん葬式なんて出してないでショウ。しかもこっちはそこに住んでるわけで、出かけて夜帰る時も入り口開けて通るわけだでも、一度もそんなもんみたことなんかないデよ。だけどお客さんみいんな数年のあいだ、気味悪がって近寄らなかったってハナシ」
紳士とふたり、そのからくりに幾つかの仮説を立て盛り上がった後、彼はタクシーの手配を店に頼んだ。北の道は凍結している。到着後、外まで付き添いタクシーまで見送る。そして己の足取りのひどさから自らも尻もちをついた。そろそろ撤退した方が良さそうだ。ようやくあきらめがつきつつも、くだらない未練が残る。
女性客に挨拶くらいはして帰りたい。
店の扉を開けるにひとしく、あるじが出てきて手刀を切り「トイレ。店番よろしく」小ぶりな店内にはない、ビル共用のそこに向かう。
微かな機会。私は、女性客にまるで興味のないそぶりで席につくあいだ、ちらりと目配せをする。そして目を張った。心は、底まで凍りついた。
女は老婆であった。オフホワイトのブラウスは正絹の死装束であった。縦結びの帯で右上前に重ね合わせられていた。うなじより低い位置に一本に束ねた白髪、深い皺に包まれた横顔は、うす闇のなか、もの憂げにおし黙る。
そこまで。ーーそこまで。
そののちのことは、どう帰ったかも含め、
いまだなにひとつ思い出せずにいる。
本日の不親切案内。
すすきのに入る手前の通りにあるビル一階「T」※会員制
そな田日記